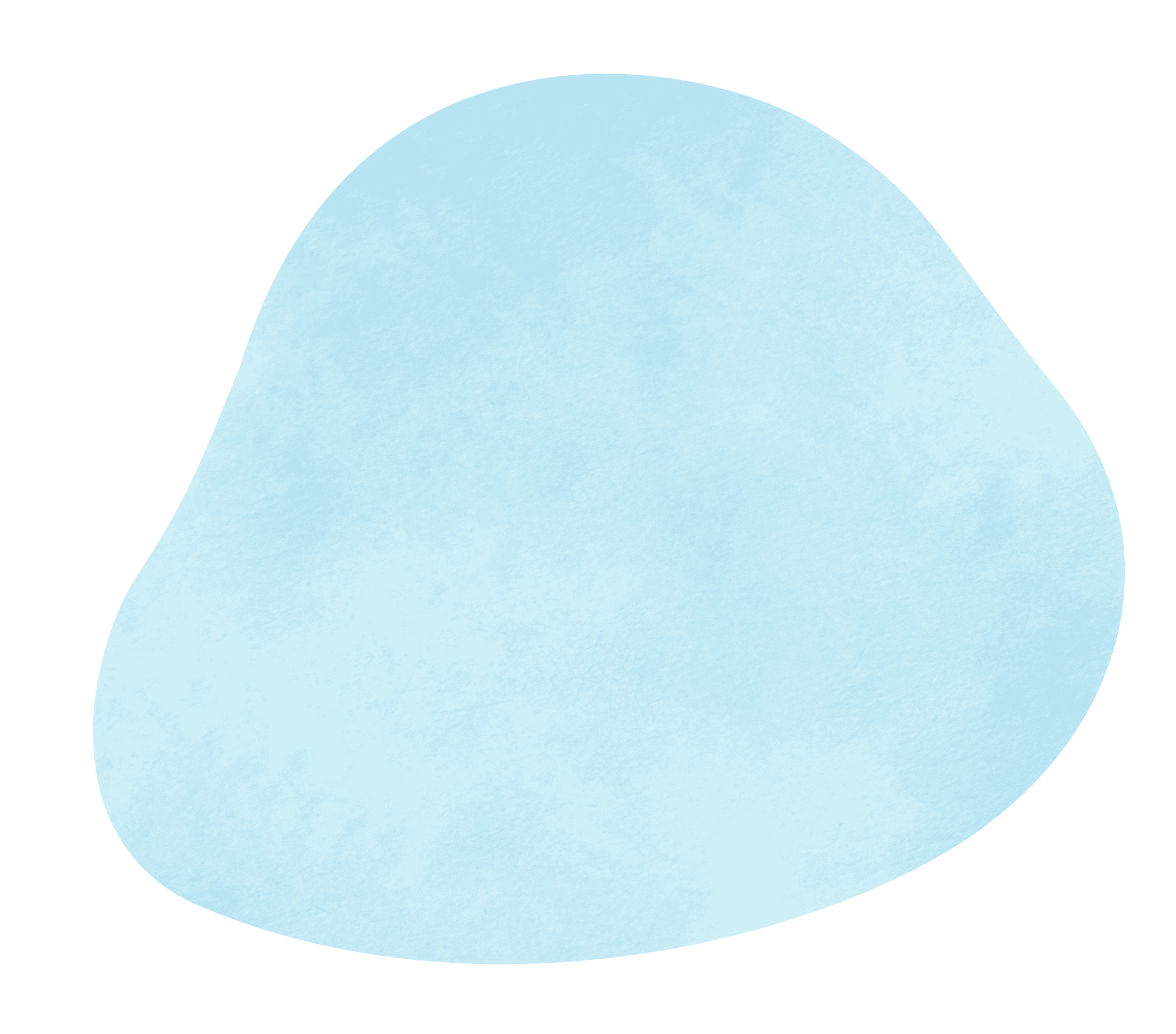老舗クリーニング店を母体とするland linkが「野菜をあらう水」を出した理由とは
朝起きてコップ一杯の水を飲むだけで、体が一気に目覚めて元気になるような気がしませんか?
暮らしのなかで、水と関わらない日は1日もありません。飲食以外にも掃除や風呂など、私たちは水と共に生活しているといってもいいほどです。
衣類などを洗濯する際にも、水は欠かせません。今年で創業79年を迎える老舗クリーニング店の次男として生まれ育ち、水の大切さや偉大さを肌で感じてきたという株式会社land link(ランド リンク)の代表取締役 蓮見知章(はすみ ともあき)さん。
「水は尊く、ときには怖い一面も見せる。とても尊いものです」と語る蓮見さんが、命を育むために開発したのが「野菜あらいのお水 ベジセーフ」。開発のきっかけや製品に込めた想い、その先の夢についてまで、熱意たっぷりにお話しくださいました。
トップの画像。(写真提供:land link)
ライフラインである水に“ド真剣”に取り組む
- 水と暮らす編集部
-
まずは、land linkさんの事業内容を教えていただけますか?
- 蓮見さん
-
私どもの主要事業はクリーニングの集配業です。というのも、実家は今年で創業79年を迎えるクリーニング店で、今は兄が継いでいます。
クリーニングには、大量の水が使われます。と同時に、しみ抜きなどのために数多くの化学物質も使われ、化学物質をしみに合わせて調合し噴霧もします。
私の父はがんを患い70歳で他界しましたが、その一因がクリーニング時の化学物質ではないかと家族は考えました。兄は、家業を継ぐ際に「可能な限り化学物質を使わないクリーニングを目指す」と宣言。僕も賛同し、兄をサポートできる仕事として集配の会社を立ち上げたのが16年ほど前です。
- 水と暮らす編集部
-
確かにクリーニングはたくさんの水や洗剤を使うイメージです。化学物質を使わずに、どうやって汚れを落とすのですか?
- 蓮見さん
-
汚れが落ちないのは、多くが油溶性で水と交わらないためです。油ギトギトのお皿に、いくらお水をかけても汚れが落ちないのと同じですね。通常は、油と水が交じり合うよう界面活性剤入りの洗剤などを用います。
家業のクリーニング店では、洗剤の代わりに水を電気分解した「アルカリ電解水(※)」を使うことにしました。アルカリ電解水は、たんぱく質や油脂を分解できるので、水洗いだけで油溶性と水溶性の汚れが一気に落とせるのです。
お客さまから「黄ばんでいたドレスが見違えるようにきれいになった」など、とても喜んでいただきました。それが今日お話しする「ベジセーフ」の原点にもなっています。
-
※水を電気分解して作られた水

- 水と暮らす編集部
-
そもそも、なぜ「ベジセーフ」を開発しようと思ったのですか?
- 蓮見さん
-
僕自身に、子どもが生まれたことが大きいですね。多くのご家庭もそうだと思いますが、お子さんができたときに、食生活を見直し、改める方は多いものです。僕は、ちょうどそのタイミングで、普通に購入する野菜などには農薬が思っていた以上にたくさん残っているものがあるということを知りました。
尊敬する父を亡くしたとき、化学物質の怖さを肌で感じていたため、「何かいいものはないか」と考え、思い浮かんだのがアルカリ電解水だったというわけです。

「うさんくさい」と揶揄(やゆ)されたことも…
- 水と暮らす編集部
-
還元型アルカリ電解水「ベジセーフ」の開発で、特にご苦労されたことは?
- 蓮見さん
-
クリーニングに使用していたときから、アルカリ電解水の洗浄力の高さは実感していたので、開発はそれほど難しく感じませんでした。ただ、環境へも人へも徹底して優しいものであることだけを追求したといってもいい。そのため、野菜を洗うためのpH(水素イオン指数)の最適値を探り、還元型にするにはどうしたらいいかにはこだわりました。
苦労したのは、まったく認知されなかったこと(笑)。発売は約7年前ですが、「すばらしい商品だね」と言っていただけるようになったのはこの1年ほどです。それ以前は、「単なる水でしょ? うさんくさいよね」と揶揄されたり、「うちで売る野菜はちゃんと基準値以下の農薬だから」と、お叱りを受けることもありました。
そのたびに、国内外の農薬基準値の違いやエビデンスを示しながらていねいに説明し、少しずつわかっていただけるように。コロナ禍で健康や食への意識が急速に高まったことで、「ベジセーフ」への見方も大きく変わったように感じます。
- 水と暮らす編集部
-
本業の集配業が順調だったにもかかわらず、なぜ「ベジセーフ」にこだわり続けたのですか?
- 蓮見さん
-
水を生業(なりわい)とする者の務めだから。水は人体の大半を占める命の源であり、生きている限り人は絶対に水を必要とします。ライフラインである尊い水を商売として扱う限り、環境や人に良いものでなければならないというのが僕の信念。だから「ベジセーフ」にこだわり続けました。
もし仮に、明日にでも世の中の農作物がすべて有機栽培になれば、「ベジセーフ」の役目は終わります。僕の最終目標は、「ベジセーフ」を売る必要がないくらい、良質な食がどこでも手に入る世の中なんです(笑)。

「おいしい」を入り口に食に関心をもってほしい
- 水と暮らす編集部
-
自社の製品が売れなくなればいいとは、大胆なご意見ですね(笑)。
- 蓮見さん
-
あははは。でも、こういう一風変わったやつがいるなと思って、ひとりでも多くの方に関心をもってもらえたらうれしいですね。残念ながら、日本での有機栽培農家はわずか0.2%ほど。すべてが有機農法の野菜になるにはまだ時間がかかりそうです。となると、「ベジセーフ」がまだまだ活躍する場はあるのかなと。
- 水と暮らす編集部
-
利用した方からの反応でうれしかったものは?
- 蓮見さん
-
たくさんありますが、“おいしい”と喜んでいただけたことでしょうか。米を洗う最初の水に「ベジセーフ」を使ったら、味も香りも別もののようにおいしくなったとか、イチゴを「ベジセーフ」で洗ったら高級品のように感じたなど、使ったご本人がとても驚いていらっしゃるようです。
これは「ベジセーフ」が味を良くしているのではなく、外側に付着していた化学物質が落ち、食材の味がダイレクトに感じられるから。土壌が豊かな有機栽培の食材にはおよびませんが、同じ食材なら、よりおいしく食べられたほうがいいですよね。
それと同じくらい驚いてくださるのが、「ベジセーフ」で洗うと野菜が生き生きとして、長持ちすること。長持ちするとフードロス問題の対策にもなるので、こちらも喜んでいただいています。おいしさや安全性の高さなどが認められ、2019年から、岩手県花巻市などの学校給食で使っていただくお話も進められています。

子どもたちに野菜本来のおいしさを届けたい
- 水と暮らす編集部
-
2021年3月に始まった「#栄養まるごとプロジェクト」に、「ベジセーフ」を無償提供されているそうですね?
- 蓮見さん
-
ええ。「#栄養まるごとプロジェクト」は、食のプロである服部幸應先生が理事長を務める「服部栄養専門学校」さんと、慈恵会医科大学附属病院栄養部課長の濱 裕宣(はま ひろのぶ)先生との協働で立ち上げました。1日分の野菜摂取量の目安は350グラムといわれていますが、それでも場合によっては栄養不足になっていることをご存じですか?
- 水と暮らす編集部
-
必要な量を食べているのに、栄養不足とはどういうことですか?
- 蓮見さん
-
それは、たいていの人が皮を捨ててしまうからです。『その調理、9割の栄養捨ててます!』などの著書が大ヒットした濱先生によると、にんじんの皮には中心部の2.5倍のβカロテンがあるそうです。
野菜や果物の栄養素は、皮周辺に集まっていることが多いので、それを捨ててしまうのはもったいない。ですが、残留農薬などの懸念から学校給食では皮をむいて調理することを推奨しているんです。
- 水と暮らす編集部
-
栄養の宝庫、皮を捨てていたとはもったいない……。
- 蓮見さん
-
そうですよね。それに、皮をむくとそれはごみになるけれど、まるごと食べれば栄養になる。日本は生ごみがとても多く、1人あたり年間約50キロも捨てているというデータもあります。皮ごと食べればフードロスの削減にもなりますし、ごみ処理の手間も減るので、調理する人の負担も軽くなりますよね。

- 水と暮らす編集部
-
この先、さらに推し進めたい計画はありますか?
- 蓮見さん
-
日本の農産物の魅力を世界に知ってもらいたいですね。フードロス問題の要因には、規格外の野菜の廃棄もあり、年間250万トンも捨てられています。
見た目が悪い野菜をパウダー状やカット野菜にして、第二の人生を歩ませたい(笑)。パウダーにすれば、輸送も簡単なので海外にも運びやすくなります。じつは、その計画はJETROさんを通じて少しずつ前進し始めています。
- 水と暮らす編集部
-
スケールが大きなお話ですね。
- 蓮見さん
-
まだまだですよ。夢は、活動をもっと浸透させ、日本中の農作物を買い占める権利をもつくらいまでになりたいという域にまで達しています(笑)。もしそうなれば、僕から農家さんにお願いして、すべてを有機栽培に変えてもらうこともできますよね。日本全国の安価で良質な野菜を流通させ、おいしく食べて健康になっていただくのが最大の夢なんです。
まとめ
-
実父の死をきっかけに、水の大切さに気づかされた蓮見さん。実家のクリーニング店の作業方法の転換だけでなく、食にまで関心が高まったといいます。命の源、水を扱う企業として、また良質な暮らしを望む一人の父親として、大きな目標を掲げ、実現のためにまい進する姿はとても頼もしいものでした。